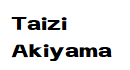歌手とメタバース
-
noteに投稿するつもりで書いた文章ですが、2022年05月18日に書き終え、そのまま1年経ってしまったのでこちらに。メタバースもSNSのように普及してきたら、また違った観点が生まれてくるような気もします。(2023年5月07日)

Charles Ives - Majority (1921)
楽譜はアメリカの作曲家チャールズ・アイヴズの歌曲『マジョリティ』の前奏部分。冒頭の四角で囲まれている箇所には、5本の指では弾けない数の音譜が集まっている。板などを使う奏法なのかもしれないが、一人の手に余るほど多くの音譜がある枠のなかに「多数者」はいるらしく、その在り方は不協和音ということかもしれない。
人物の変容
ボーカロイドやVTuberといったバーチャルな存在が現れてから、歌手は情報に近くなったように思う。ボーカロイドは情報のなかだけにいて、人間にしかできなかった歌を、たとえその歌声に未完成なクセがあっても、歌うことができる。少なくとも情報のなかでは、ほかの歌手と同じように、ボーカロイドも歌手なのだ。このことは、ネットやメディアなどに登場する人物たちについて、実際に会ったことがなくても、彼らはどこかで暮らしている実在する人物なのだという確信を、微妙に揺るがしてしまう。モニタに現れた人物はカメラなどで実像を捉えたものに違いないが、結果的にそれは情報がつくりだしているのだという認識のほうへと傾いていく。

AIが生成したアニメ画(『This Anime Does Not Exist』より)
写真や映像、あるいは録音された声などは、この現実で起きたオリジナルな事象をコピーしたもので、それは複製技術によって可能になったものだった。ポップ・カルチャーは、アンディ・ウォーホールの作品にみられるように、コピーが氾濫すると、オリジナルが消失する、そういった状況のなかで生まれた。それは、既存メディアのなかで起きていた事態だ。しかし、複製されることで失われたオリジナルは、かつて、この現実のどこかにあったはずのものには違いなかった。その意味で、複製された情報は、ある時期までは、まだ、オリジナルへとたどり着くことができる道筋を隠していたといえるかもしれない。
架空のコンサート
1967年に発売されたビートルズのアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』は、すでにコンサート活動を中止していたビートルズが、レコードという媒体を使って自らを虚構化して作り上げたコンセプト・アルバムだった。演奏者は「ビートルズ」という実在するバンドだが、「サージェント・ペパーズ」というアバターとなって虚構化されてもいる。ジャケットには大勢の人々が集まって、サージェント・ペパーズの服を着たビートルズを取り囲んでいる。そこには、ボブ・ディラン、シュトックハウゼン、ウイリアム・バロウズ、マリリン・モンロー、ジークムント・フロイト、エドガー・アラン・ポー、アインシュタイン、ルイス・キャロル、そしてデビュー当時のビートルズ自身など、実在したさまざまな分野の著名人たちが一堂に会している。まるで集合写真のようだ。しかし、彼らは実際に集まったわけではなく、顔写真がコラージュされた虚構のアートとなっている。

Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)
アルバムの終盤、タイトル曲「サージェント・ペパーズ」が再演奏されることで、架空のコンサートは一旦幕を閉じるのだが、すぐあとに続く「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」から、虚構の祝祭空間は、その外側に存在していたはずの日常的な視点へと変換される。しかし「人生の一日」は、「サージェント・ペパーズ」という虚構とつながって、ますますバーチャルなクライマックスに昇り詰めていく。この、メタフィクショナルな感覚は、1960年代のカルチャーやヒッピー・ムーブメントなど、当時のビートルズが置かれた状況が、ねじれたミラー・ワールドのようにアルバムの内側へと入り込んでいるという感覚とも相まってくる。現実がフィクショナルに多層化して日常性が虚構じみて感じられるのは、テレビなどのマスメディアが広範囲に拡大していた時期とも重なっていたからだろう。
このアルバムは、4トラックのテープレコーダーを2台使い、それを同期させてミックスすることによって制作された。つまり録音テープというメディアを2倍にして作られている。冒頭で聴かれる観客の歓声にしても、ライブ演奏の収録ではなく、テープ編集されていることに意味があると思う。というのも、このアルバムは、観客も演奏者もメディアを通して関係しているという認識を、やはりメディアであるところの「録音」という技術を駆使してフィクショナルに実現させた音楽だといえて、それをアートへと近づけた初期の試みでもあったからだ。
ところで、サージェント・ペパーズの演奏を聴いている「観客」という存在とは、ポピュラーな大衆のことでもあった。音楽がポピュラーなものとして成立できる所以は、個人から発せられた歌が、彼女/彼らが所属するコミュニティのなかでどれだけ伝わるかということに関わっていたはずだ。大衆のなかにいる個人が、「大衆のなかの大衆」として登場し、その大衆と流通することでポピュラリティーは生み出される。個人と大衆は同じではないけれど、大衆との共同性をあらわす存在として現れてくる。
電子大衆
部屋にあるスピーカーから音が出る (電気信号に変換された波形が増幅されて、音声となって出力される)というようなことが、エレクトロニクスの進歩によって可能になったという時代的な背景がまだ目新しく、濃厚に感じられていた時期には、電気技術がつくり出す共同的な価値とコミュニケーションが人びとのなかに生じていたのかもしれない。「音楽を聴く」ことのなかには時代の技術と結びついた価値があって、それはある種のオーラのようなものを生み出していた。このオーラは製品化された電気機器から醸し出されていた。テレビやラジカセ、ステレオ装置といったものだ。真空管やトランジスタによって、歌手はブラウン管のなかに映像となって現れ、彼女/彼らが歌う音楽が部屋に流れてくる。電気製品から聴こえる声の持ち主は実在していて、録音によって複製された波形が音声として聴こえていた。
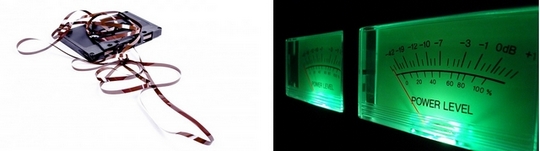
音声(オリジナル)→録音/再生(波形)→複製(コピー)され、再現された音声
やがて、音楽がデジタル流通に置き換わってからは、音声の元となっていた波形は符号化されて、数値に還元されることになった。デジタル化は音楽を含めたすべてのメッセージを[1と0]からなるデータに置き替えるから、画像や文字、音声といったメディアによる違いは、モノという次元では差異がなくなってしまう。音楽を受容することで生まれていた特別なオーラは、一台のPCやスマホですべての情報が扱えるようになってからは薄まったといえるかもしれない。レコード・プレーヤーやアンプなど、アナログ時代にエレクトロニクスが実現した電気製品には個性があったけれど、いまでは、差異はモノにではなく情報にあるということになっている。あるいは情報とは差異そのものだともいえて、デジタルの世界に現れた何かを読みとっている「あなた」や「わたし」が、そこに意味を見出す固有な存在として残ることになる。
そんな「あなた」や「わたし」の姿は、スマホに備え付けられたカメラによって、声はマイクによって電気信号に変換され、変換された信号はさらに数値に置き換わって電子空間を移動する。その過程で人びとは世界のどこにでも現れることが可能になり、かつて大衆といわれた存在は大規模に分散された。その様態は[1と0]が並んだデータであって、データの世界では実在・非実在の違いがなくなる。というのも、情報を成り立たせているものが[1と0]からなる配列なら、モニタに映る「あなた」の姿はオリジナルのコピーというより、変更可能な数の組み合わせから出来ていることになるからだ。これまで実在する人物として舞台に登場してきた歌手たちは、バーチャルな空間にいる人形の存在となってスマホなど小型の装置のなかから登場する。電子の世界に分散された大衆とボーカロイド。彼女/彼らが歌う音声は、細かくスライスされたグレイン(粒子)となって、選択された波形のなかを自在に動き回ることが可能だ。
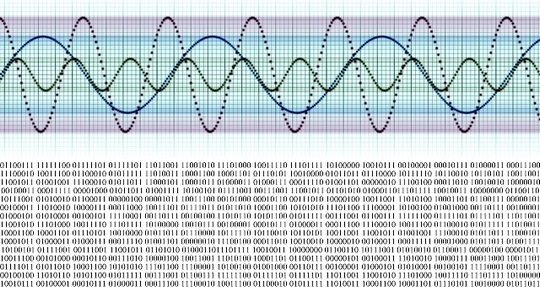
情報がすべて数値からできているということは、数値によってすべての情報が構成できることでもあるから、自律した世界は計算によって成立可能になるわけだ。それを仮想空間と呼べば、「わたし」はアバターとなってその世界に入り込んで、やはりアバターとなった「あなた」と共同作業ができるようになる、といわれているのがメタバースだ。そこはゲームの世界に似ているけれど、現実のコミュニケーションと同じことが行えるという。コラージュされた架空の世界はひとときの余暇を提供するためにあるのでなく、遊びや社会活動の場として街があり、店があり、オフィスがある。これら、データがつくる架空の世界のなかで「わたし」は現実の仕事をするのだ。ここには、虚構と現実の入れ子状の関係があると思う。
入れ子状の世界
仮想空間は、この現実をパラフレーズした世界でもあって、そこは「世界のなかの世界」ともいえるフレームを持っている。多層に重なるいくつものレイヤーがある感じだ。これは、劇のなかに劇があるような物語を思わせたりもする。古くはシェイクスピアの『真夏の夜の夢』などがそうで、劇のなかで「ピラマスとシスビー」という別の劇が演じられる場面がある。こういう手法を劇中劇と呼ぶのだけれど、劇だけでなく、映画にも、劇中劇は多かった。古典といえるゴダールの『女と男のいる舗道』では、主演のアンナ・カリーナが映画館でサイレントの名作『裁かるるジャンヌ』を観るシーンがある。映画のなかで映画を観ているのだ。それは別の映画の引用ともいえる手法だけど、虚構のなかに別の虚構が含まれたうえで一つの作品が成立している。虚構内にさらに虚構があるから「メタ」なフィクションとされるわけだけど、こういったメタフィクショナルな方法論は広く普及して、SFなどではおなじみのものになっている。

Jean-Luc Godard - Vivre sa vie: Film en douze tableaux (1962)
情報がつくる仮想現実のなかで「わたし」は暮らしている――まるでSF映画のようだけど、今後はネットを介したデジタル技術が実現し、社会や経済、生活のなかに実装されていくのだろう。日常と接続されたその世界に入り込めば、アルゴリズムが計算した3次元空間を体感できるわけだ。ところでメタバースの特徴は、そこが「空間」だということがあるかもしれない。映画やアニメといった虚構内の現実は2次元だったわけだけど、次元が一つ増えた分、世界の細部を成り立たせるのに必要なデータ量はこれまで以上に膨大になるはずだ。ネットの進化を可能にするのは、より速くデータを流通させるためのスピードかもしれない。
データが流通する電子空間はいわば深層の世界で動いていて、そこでは、人工知能が外部化された意識のように判断を行う場所でもある。深層は[1と0]の数値から出来ていて、無意識のように世界の背後に隠れている。仮想世界を訪れる「わたし」や「あなた」にとって、その「空間」は自律した世界であるように感じられることだろう。そんな自律した世界の精度が上がれば上がるほど、それを生み出している機械の自律性もより強化されていくはずだ。機械が自律していくほど、多種多様でリアルな異世界が生み出される。それは、脳に直接電極が接続されて夢を見ているような現実に近くなる。ブレイン・マシン・インターフェイスにつながった「わたし」が、そういう過去のSFを思い出す日が来るかもしれない。

超弦理論の分野である「ホログラフィック原理」によると、この宇宙は2次元の上に描かれたものだという。情報量は体積によってではなく、表面積によって定められている。そのため、3次元の立体的な物理過程は、2次元境界面によって定義された別の物理法則によって記述可能だとされる。ネットの接続を切ってゴーグルを外せば、仮想現実から普段の日常へと戻るわけだけど、「わたし」が暮らしているこの現実もまた、別の情報がつくり出した仮想世界かもしれないという反転した考えが、SF映画によってではなく、現代物理学によって後押しされることになるのだ。宇宙が2次元の情報からできているというこの世界観は、3DCGによる仮想空間のような世界が、入れ子状にこの現実をも形作っているかもしれないという感覚を生みだす。
2019年のアニメ作品『HELLO WORLD』では、10年後の主人公がアバターとなって仮想世界に生きている自分に会いにくる。その目的は運命を変えるためで、目的を達成して10年後に戻ると、そこも仮想世界で、因果関係を変更したことと、同じ世界に二人の自分は存在できないことから自動修復システムが働いてしまう。時間を変えることで世界は変更されていくのだが、このマルチバース化した世界は、コンピュータによる情報によってつくられているからメタバースでもあるといえるような設定になっている。二つの世界に存在する「わたし」は、年齢も違えば、ときに別人格のように争うことにもなる。メタバースに暮らすもう一人の「わたし」は、この「わたし」と似ているのだが、同じではないのだ。
-
1. わたしと同じわたし
2. わたしと似ているわたし
人生の物語としてのあなた
これまで、物語は、映画や小説、マンガやドラマのなかにあって、その多くは2次元の虚構作品だった。対して、虚構ではない現実は3次元のはずだった。しかし、この3次元空間もまた、2次元の情報から構成された世界だとしたら、身体を通して感受しているこの空間とは、意識がそういう空間性のようなものを感じ取って理解した結果にすぎないとも思えてくる。この世界が何らかの法則によってつくられた情報で、空間もそういった情報の一つなのだとしたら、その情報を感知している意識が3次元だという理由もなくなる。また、時空も含めたあらゆる事象が公理として書き換え可能な法則から出来ているとすれば、それは計算によって変更可能な余地を含んでいることになるかもしれない。

とはいえ、たとえそうだとしても、「あなた」や「わたし」がどこかに暮らしていて、人生を送っているという現実は変わらない。ネットを介したデジタル世界のSFじみた加速度と比べると、ネットから目を離した現実は鈍く停滞していて、ポテンシャルの大きなギャップを感じる。時間は、目的論的にはループしながら、因果的には開かれていく。「終わりは始まりに戻るけど、元いた位置には戻ってこない」と、VR空間に現れたメタシンガーが歌う。2次元の虚構世界のなかにあった物語は、メタバースによってこの現実に接続される。それは人生の物語として。
(了)
-
1. わたしと同じわたし