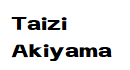1. 見たものを、見たままに言葉で誰かに伝えることは可能だろうか?
見たものを、見たままに言葉で誰かに伝えることは可能だろうか? たとえば、下の図を見て、これを誰かに伝えるには、

「正三角形」といえばよさそうだ。仮に、この三角形の一辺の長さが3cmだとしたら、「一辺が3cmの正三角形」といえば、この図は正確に言葉で表すことができる。「一辺が3cmの正三角形」という言葉があれば、それを図示しなくても、上にある図形の形は誰にでも伝わるはずだ。
● 写真に写っている景色
では、どこかへ外出した際に見た景色を言葉で誰かに伝えるには、どのように話せばうまく伝わるだろうか。言葉で説明するよりも、写真を撮ってきて、それを見てもらうほうが手っ取り早いんじゃないだろうか。たとえばその景色が下の写真だったとする。

この写真を見てもらえば、それがどんな景色なのかということが伝わる。でも、もし何かの事情で写真を提示できなくなったとして、上の景色を言葉だけで誰かに説明する必要があったとしたら、どんなふうにいえばよいか。
「そこは雑居ビルや古めかしいマンションなどが乱雑に建ち並んでいる裏寂れた街中で、遠くまで建物が地面を埋め尽くしています。その向こうの白い空には低い山が霞んで見えています」
この説明だけを聞けば、ある程度、それがどんな景色なのかをイメージすることはできるかもしれない。漠然となら、なんとなく「そういった感じ」ということは伝わると思う。でも、この説明だけを聞いて上の写真とまったく同じ景色を思い浮かべられる人は皆無だろう。なぜ、「一辺が3cmの正三角形」のときと同じように上の写真が言葉で正確に伝わらないのか。写真に写っているものが複雑すぎるためか。それならば、さらに正確に説明していけば、カメラのピントが合っていくように上の景色のイメージも正確になっていくものだろうか。
-
「そこは雑居ビルや古めかしいマンションなどが乱雑に建ち並んでいる裏寂れた街中で、遠くまで建物が地面を埋め尽くしています。その向こうの白い空には低い山が霞んで見えています。さて、左側には二件のマンションが並んで建っています。二件のマンションは似たような造りの建物で、高さはほぼ一緒です。でもよく見ると微妙に形が違っていて、表側の壁はそれぞれ緑色とオレンジ色に塗られています。オレンジ色のほうは最上階からその下の階にかけて外壁が斜めに傾いています。窪んだ窓はベランダになっているようです。屋上には白い給水塔が乗っかっています。それは、ふたつのマンションのほぼ同じ位置にそれぞれ置かれています。マンションの手前には雑居ビルの屋上があって、黒く尖った形がマンションに向かって突き出ているように見えます。その狭い面積には物置や青っぽい給水管のようなものが配置されていて、向こう側のビルの壁面が手前のビルよりも高く延びて小さく視界をふさいでおり、ごちゃごちゃとその向こうにも古めかしい雑居ビルが何件か重なりあっていて、……」
こんなふうに言葉を連ねていけば、どんどん上の写真と同じイメージが頭のなかで明確になっていくなんてことは、ちょっと考えられない。それは、説明の仕方が下手で、まだまだ言葉が足りないからだろうか。いや、たとえ原稿用紙1000枚分の言葉を使って説明しようとしても、上の写真を見てない人に、まったく同じ景色を伝えることはできないといえる。どこまで言葉で細かく説明しようとしても、それは難しい。たとえば、「マンションの外壁は少し黒っぽく薄汚れています」と相手に説明したとする。そのとたん、「少し」というのはどの程度なのか、「薄汚れている」状態は具体的にはどう汚れているのか、説明しきれていないことに気付く。そういったことをさらに細かく説明したとしても、その光景をあたかも目の前で見ているかのように相手に伝えることは、ほとんど不可能だ。
2. 描写を徹底させようとしたら文章には終わりがなくなる
[例文]そこは雑居ビルや古めかしいマンションなどが乱雑に建ち並んでいる裏寂れた街中で、遠くまで建物が地面を埋め尽くしています。その向こうの白い空には低い山が霞んで見えています。
● 言葉とイメージ
上の[例文]を読んで、なんとなく「そんな感じ」といった光景を思い浮かべたり、人によっては、具体的に知っている場所がはっきりと目に浮かぶかもしれないけれど、実際に[例文]で言われている場所がどこか知らなくても、この説明だけで「イメージ」が頭の中に表れたとしたら、それは、この文章を読んだ人の記憶が何らかの連想を引き起こしたからだといえる。たとえば、「正三角形」という言葉を聞けば、たぶん、100人が100人とも同じ図形を思い浮かべるはずで、なぜなら「正三角形」という言葉から喚起されるイメージというのは「2+2=4」という数式と同じくらいに確定的で、融通が利かないものだからだ。
これに対して、上の[例文]を読んで、100人が100人ともまったく同じ景色を思い浮かべることはまずあり得ない。人それぞれ、文章から連想されるイメージは異なるはずだ。でも、それらのイメージは、まったく無規定に生み出されるわけではなく、[例文]という具体的な文章から生み出される。それは、「街中」とか「建物」とか「低い山」とかいった具体的な言葉が使われた文脈によって規定されている。「正三角形」という言葉のように正確に何かを規定しているわけではないから、かなり曖昧なものには違いないけど、「枠組」というのか、ある程度の限定性を伴った文章には違いない。
ただし、仮に100人が読んだとしたら、中にはこの文章から「砂浜」の光景を突拍子もなく思い出す人がいるかもしれない。たとえ文章に「枠組」というものがあっても、それを読んだ人が何を連想するのかといったことまでは予想できない。ここでは、予想できないことまでは視野に入れないことにするけど、文章には、「2+2=4」というように初めからたったひとつの解答が決まっていて、誤読とか勝手な解釈とかを許さないようなものとか、反対に自由な解釈を許す文章、つまり「詩」のようなものがあったりする。
● 詩的なものと小説的なもの
[例文]は「詩」とは程遠い素っ気ない書き方だけど、いわゆる「詩」というものは一般に、自由なイマジネーションを喚起するように書かれている。つまり、言葉と言葉の関連から引き起こされる連想の効果を最大限に高めるよう努めるために、そこでは比喩や象徴が駆使されるといえる。ここから生み出されるものが詩的イメージといわれるもので、これは想像力というものにつながっていく。しかし、ここで考えたいのは「描写」についてである。
[例文]は、そもそも上の写真を言葉で説明したものだったけど、この光景そのものを、そのまま正確に言葉に移し変えることができないということは、この写真の景色は言葉で表現できる範囲の外側にあるということだ。これは、目の前のこの光景が理解できないから説明不足になるわけではなく、仮にそれがどんな景色かということを完全に把握し、理解できていたとしても、それを言葉で表すには、いくら言葉を費やして説明しても現実のこの景色には届かない、いくら説明しても言い足りなくなるということである。つまり、「描写」というのは言葉の内側だけで完結させることができないもので、言葉の外部との関わりがあってはじめて成立するものだといえる。だから「描写」を徹底させようとしたら文章には終わりがなくなる。
とはいえ、実際に文章を書いていけばどこかで終わらせなければならないわけで、たとえば[例文]はある光景(写真)を短い文章で「表現」したものだといえるかもしれない。でも、たとえ原稿用紙1000枚を使って文章を完成させ、そしてその文章がすごくうまく書けていて、さらに何かを「表現」できていたとしても、「描写」という観点から考えた場合「完全」な文章というものはあり得ない、それは常に「不完全」なものだといえる。これはつまり詩の話というよりも、小説的な話になっていくのだと思う。
3. ある場面を対象として選びとること
小説の書き出しの文章を考えている作者は、自分と社会との関係を選ぼうとしている人の姿に似ている。何らかの場面を対象として選び取ったということから、小説の文章は始まるのだ。描写は「選択」の問題に通じていると思う。ある場面を対象として選びとること。これが、描写のはじまりではないのかと思うからだ。このことについて考えるために、つぎの絵を見てみたい。

上の絵は、両方とも19世紀フランスの画家マネ(1832-1883)の絵だ。かなり写実的な描き方をしていて、遠近法的な描き方をしているようにも思うけど、にもかかわらず、それ以前の絵画とはまったく違った印象を受ける。
● 表現と描写(ドラクロワとマネ)
例えば、下の絵は19世紀フランスの画家ドラクロワ(1798-1863)の『民衆を導く自由の女神(1830)』で、やはり写実的な描き方をしていると思うけど、しかし、マネよりも一時代前という気がする。

一目みて、いったいどこが違うのかというと、ドラクロワのほうは革命というものを「主題」にしていて、そのような「主題」を表現するという意図から絵が描かれている。そのために、実際にこんなシーンはあり得ないようなデッサンになっている。対して、上のマネの絵は、まるでどこにでもありげな日常をスナップ写真で撮ったかのような、あるいは、あたかも映画のワン・シーンであるかのような絵だという気がする。これらの絵を比べてみると、ドラクロワは「表現的」、マネは「描写的」だといえるんじゃないだろうか。マネの絵は、それこそ、日常からある場面を対象として選びとっているかのような絵画だ。ほとんど「写実的」というより「写真的」というのか、一枚目の絵は120mmくらいの望遠レンズで、二枚目は50mmくらいの標準レンズで撮影されたかのような遠近感を感じる。絵画についてすごく詳しいわけではないのだけれど、たぶんこういった感じの絵というのは、それ以前の絵画にはなかったものではないか。いわゆる三次元遠近法といっても、マネの絵は、それ以前のものとはだいぶ違う。
● 機能和声と「奥行き」
そもそも、絵画における三次元遠近法というものはヨーロッパで15-6世紀あたりから成立したものらしい。これは、音楽において機能和声(TDS)がつくられていくことと重なっている。16世紀バロック前期のモンテヴェルディは、それまでのポリフォニーをとらずに、今日に繋がるようなさまざまな和声による調性音楽を作りあげた。調性音楽というのは、ひとつの中心になる音、つまり主音(トニック)というものがあって、そこに五度と四度を加えた三つの音を基礎にして成り立っている。同様に絵画における三次元遠近法にも、ひとつの中心になる点があり、つまり無限遠点というものがあって、そこに向かって線を引くことによって、二次元の上にあたかも距離(奥行き)が生まれるような絵を描くことができるという技法だ。
ここで「奥行き」が生まれるということは、音楽に長調・短調があることと同じくらい重要で、というのも、そういった技法上の問題は、大きな物語とか、歴史とかいった社会的な制度と強く結びついていたはずだからだ。それが、上のマネの絵では、その対象物や遠近感などが「写真的」になることで、それまでの制度的なものから逸脱しているという印象を受ける。今に繋がるような、現代的な観点が垣間見られる。もし、「近代」というものをデカルトあたりから始まっていると考えれば、音楽でいえばバロックくらいの時期になるので、機能和声とか三次元遠近法とかいったものも「近代」に含まれてくるといえるけれども、19世紀後半に描かれたマネの絵は、その後の観点を示している。
4. 主題はゼロ記号として残っている
ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』は、革命という激動の時代を「主題」にしたものだから、大きな物語性のある歴史といったものが表れていると思うけれど、マネの絵では、王を倒したあとの平和な日常といったものが描かれていて、ドラクロワの絵のような大きなテーマは見当たらない。そこに見られるのは市民的なありふれた場面だ。時間的にも、ドラクロワが出来事の流れを一枚の絵に凝縮したような描き方をしているのに対して、マネでは出来事の一場面だけを切り取って描いているかのようである。
しかしこのことは、あたかも、王がいなくなったあとも、主題はゼロ記号として残っているかのような思いを起こさせる。というのも、マネの絵にはドラクロワの絵にある物語(出来事の流れ)はないように見えるけれども、絵には描かれていない部分にストーリーというものがあるような感じを起こさせるからだ。それが見えない位置で対象を規定しているゼロ記号であるかのように感じられるのだ。マネの絵では、「主題」というものがなくなったのではなくて、ゼロ記号として存在しているといえるかもしれない。
● 音楽と主題の変遷
バッハ
音楽でいえば、たとえばバッハの『音楽の捧げもの』は18世紀の、まだ王がいる時代の作品だけど、この作品はあるひとつの「主題」をもとにして書かれている。それは王から与えられた「主題」で、 8小節の半音階が混ざったハ短調の旋律だ。このひとつの「主題」から、バッハは16曲をつくって王に捧げた。それらは、フーガ、ソナタ、カノンなどの形式のものが含まれ、カノンはさらに逆行カノンとか螺旋カノンといったいくつかの形式、そして最後は無限カノンというもので終わる。ここには王がいて、「主題」がある。なにしろその主題は他ならぬ王から与えられていて、それが16曲すべてのもとになっている。ただし16曲のそれぞれは異なるタイプの曲である。聴いてみると、半音階的な進行が多く聴かれ、それが独特の感じを醸し出していたりして一筋縄ではいかない気がする。とても興味深い作品だけど、王というたったひとりの人物を中心とした世の中がまだ終わってない作品でもある。
ベートーヴェン
中心に位置する王がいなくなったあとに近代というものが始まることを考えると、ベートーヴェンあたりからそうなっていくんだろうとは思うけど、つまり、もはや王に頼れない時代に、ベートーヴェンというたったひとりの個人が巨大な音楽を構築して、それだから彼は「偉大な人間」と呼ばれることになる。ものすごい情熱と努力によって髪の毛を掻きむしりながら音楽を創造し、耳が聞こえなくなるなどの苦難にさえ打ち勝って音楽をつくりあげた人物だというイメージがある。たったひとりでそのような偉業を成し遂げた人間=市民の代表者として、たぶんベートーヴェンは理解されていると思う。

交響曲第五番は「運命」というサブ・タイトルがついているけど、「運命」が主題というわけではなくて、上の譜面が「主題」である。あらかじめ定められたマニュアルのようなものを使って書かれた曲ではなく、形式の生成が起きているような唯一無二な感じがする曲だと思う。
ドビュッシー
また、ベートーヴェンよりあとに出てきたドビュッシーでは対位法というものが使われておらず、それによって「主題」というものが曖昧になっていたり、消えてしまっているかのような感じがでてくる。ドビュッシーにはソナタ形式のように曲を規定する強固な枠組が感じられないから、曲が発展していかないような感じもする。出来事の流れがストーリーにならないまま、一瞬が長く引き延ばされたかのような感覚というか。そこには、古代とかアジアなどを喚起させる旋律なども含まれていて、いわば主題的に発展してきた歴史の外側にある無時間なものを呼び起こさせる要素もあるようだ。だから、神秘的に捉えられることもあるのかもしれないが、実際に聴くと、かなりというか、猛烈に手の込んだ作りで、新しくて、自覚的につくられた音楽だと思う。
とにかく、ドビュッシーでは明確な「主題」というものが消えていく傾向にあることが、マネの絵などに見られる特徴となにか関連はあるという気はする。印象派と呼ばれた画家が事物の輪郭よりも光を重視したことと似ているのかもしれないけど、ドビュッシーもソナタ形式のような枠組に重きを置かなかった。そこに、描写的な面があるのかもしれない。
5. 「そこにモノがある」という感覚が薄れてくる
印象派と呼ばれる絵画について考えるために、下の2枚の絵を見比べてみよう。

● ニコ・ピロスマニ 「バトゥミ」
両方の絵には、どちらも海の景色が描かれているけど、パッとみた感じからして相当に違う、というか、そういう絵を選んでみたんだけど、まず、左側のほうは、全体的に色が濃い。海や空の青さが濃密で、青黒く閉ざされた空間を感じさせる。夜なのか、あるいは分厚い雲に覆われていて暗いのか、しかし、水平線の向こうの空は明るく、絵に描かれた世界の向こう側に光のある空間が存在していることを感じさせて、それがこの絵の「奥行き」となっている。遠方は、閉ざされているのではなく、開けているのである。しかしそれは水平線の向こう、ずっと遠くなのである。
さて、海岸に面した崖には建物が連なっていて、そこに街がある。つまりそこは人の住む世界であることがわかる。切り立った岸壁や海によって街は閉ざされているけれど、その手前のトンネルから汽車が走り出てきている。そして、海面には何艘もの船が浮かび、ほかの土地へと繋がる交通手段が存在している。それらはどこか別の街へと人々を運んでいき、また、なにか新しいものが街に届くことになるだろう。絵に描かれた事象は、外界から閉ざされていながら、遠方はどこか広い世界に通じている空間で、そこには閉ざされた街があって、でもそこで暮らす人々は、汽車などの交通手段によってほかの街へと繋がっているというものだ。
さらに、この絵で特徴的なのは、遠近法が正確ではないことがあると思う。たとえば、トンネルから出てきている汽車の遠近感の妙な感じだとか。船の上に立っている船員たちの姿が手前の汽車と比べてチグハグな大きさになっているとか。こういうところは、あまり洗練されてないというか、まるで子供が描いているような感受性がある絵だけど、ここでは、たとえ船の上に乗っている人の姿が遠近法的には不釣り合いなものであっても、そういった技法上の問題より、画家の感性のほうが優先されている。厳格な作図法を無視しても、画家の描きたいものを描きたいように描くところに力点が置かれている。
遠近法というのは、たとえば「三角形の内角の和は180度」というのと似ていて、誰にとっても普遍的で同じ世界が描けるということを前提とした絵画上の法則のようなものだと思うけど、この絵では、そういった「誰にとっても共通な世界であるべき遠近法」というものが重視されていない。そのために、この絵はそういった共通の世界観からはみだした「内面」のようなものが出てきているようにも思える。「誰にとっても共通な世界であるべき遠近法」というものが、「この世界では誰もがこの法則に従わなければならない」となったら大人の不自由さを感じるんだろうけど、この絵にはそういった遠近法に縛られる以前の子供時代のような自由で無垢な感性が貫かれているようだ。
さて、いったいこれは誰の絵かというと、ニコ・ピロスマニ (1862-1918)の「バトゥミ」(黒海にある港湾都市の地名らしい)。ニコ・ピロスマニはグルジア(ロシア)の画家で、原始主義(プリミティヴィズム)と呼ばれている。原始主義の画家で有名なのはアンリ・ルソーだけど、たぶん、原始主義って、今でいうところのアウトサイダー・アートに近いんじゃないかと思う。
● ジョルジュ・レメン「ハイストの海岸」
つぎに右側の絵。砂浜のようだけど、なんだか、古い印刷物のように粒子の粗いザラザラした感じがある。しかも、黄色や赤い色の感じが、まるでコンピューターで色補正したかのような特徴的な色合いになっている。それは、この絵が点描画という手法によって描かれているからで、この絵の作者は、ジョルジュ・レメン(1865-1916)という人。先のニコ・ピロスマニとほとんど同時期の人だ。ジョルジュ・レメンは新印象派の画家で、出身は、ベルギーということだ。ちなみに、新印象派で有名な画家ではスーラがいるけど、ジョルジュ・レメンのこの絵が説明するのにわかりやすそうなので、挙げてみた。淡く、平面的な感じのする絵だ。これは、点描画という手法の特徴で、光を重視した描き方らしい。このような描き方をすると、きっと、事物の輪郭ははっきりしなくなる。事物の輪郭がぼやけてくれば、その実在感は希薄になるはずだ。つまり「そこにモノがある」という感覚が薄れてくる。
ニコ・ピロスマニの絵には、汽車とか船とかいろいろな事物がくっきりと描かれているけれども、ジョルジュ・レメンのほうは、先端の尖ったものが砂浜の上に立っている姿があるほか(船だろうか?)、全体の構図は、砂浜、海、空、雲によってやや並列的に分けられているくらいで、単純なものだ。でも、後の抽象絵画のように、具体的な事物そのものがなくなってしまっているわけではない。モンドリアンとかだと線と色のほかは何もなくなってしまうけれど、ジョルジュ・レメンのこの絵では、少なくても「海」とか「雲」とかいった現実に存在する景色が描かれていることはわかる。ニコ・ピロスマニと比べると、抽象度はグッと高くなっているとは思うけど、そこに何が描かれているのかわからないほどではない。
● テレビとモザイク構造
たとえば、ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』には、銃を持って立つ人々を率いる「女神」の姿が描かれている。「女神」というのは空想上の存在で、この絵では現実に存在しないはずの「女神」が写実的に描かれているところが19世紀的な気もするけれども、この「女神」の意味は、自由とか、人間の開放などを象徴したもののはずだ。そういった「主題」を表現するという意図のうえに、この絵の構図は出来上がっているから、この絵は写実的ではあっても写生的には見えない。
ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』は、まず先に「言い表わしたいもの」があって、それを「表現」するために構図などが決められているといえるけど、風景とか事物といった対象物がまず先にあって、それを写し取っていくような描き方をジョルジュ・レメンのほうはしていると思う(実際にどのように描いたものかはわからないけれども)。ただ、その絵は色合いということによって事物が表わされているために、事物の存在を規定する輪郭は明確ではない。対象物の距離感はないわけではないけど、「奥行き」があまり感じられない。「奥行き」が感じられないのは、絵全体が粗い粒子に覆われているかのようにぼやけているからだと思う。まるで、クリアな画像を色変換してからノイズを被せているかのようにも見える。そのために透明感がない。粗いザラザラした粒子が、古いテレビ画像を思わせもするのだが。マクルーハンはこんなふうに書いている。
-
モザイクは、踊りと同じように見ることはできるが、視覚的に構造化されているのではない。視力の拡張でもない。モザイクは、画一的でも、連続的でも、反復的でもないからだ。モザイクは、触覚的なテレビ映像と同じように、非連続的、非対称的、非線条的である。触覚にとっては、すべての事物が唐突なもの、逆らうもの、はじめてのもの、余計なもの、未知のものである。G・M・ホプキンズの「まだらの美しさ」は、触覚が感じとったものをカタログのように列記したものである。この詩は非視覚的なものの宣言であり、セザンヌ、スーラ、ルオーと同じように、テレビを理解するうえで不可欠の手がかりを与えてくれる。現代芸術の非視覚的モザイク構造は、現代の物理学や電気情報パターンの構造と同様に、対象から距離をおく態度を許さない。テレビ映像のモザイク形態は触覚と同じように、存在全体の深層における参加と関与を要求する。これにたいして、文字文化は、視覚的な力を拡張することによって、時間と空間の画一的な組織化を実現し、心理的にも社会的にも、非密着、非関与の力をわれわれに授けたのであった。
「テレビ」『メディア論』P349
ちょっと横道にそれるけど、マクルーハンは上のエッセイのなかで、固定的な視点と三次元の視野があるのは文字文化のほうで、それに対してテレビは二次元の文化であるといっている。
本
どうして文字文化が三次元なのか、どこかに書いてあったかどうか思い出せないが、たぶん、「本」という出版物の形態によるものだろうと思う。文字は紙という二次元の上に印刷されたものだけれど、たくさんの紙(ページ)が束になって綴じられた「立体物」が本である。本を読むという行為は、まず表紙を開き、ページをめくっていきながら、書かれた文字を目で追っていくことだ。表紙があるということは、そのなかに内容が詰まっていることを表しているから、深さや奥行きに関わってくるだろうし、ページをめくるという行為は、紙(ページ)が平面ではなく立体的に動くことを悟らせる。そんなふうにページを何枚もめくっていきながら文字を目で追っていくということが、「固定的な視点と三次元の視野」というものになるのだろう。つまり印刷された文字は平面だけど本は立体であって、そこには奥行きまで含まれている。本を読み終えて表紙を閉じれば、今まで読んだ内容も一冊の本の中に「閉じられる」から、そこに「内面」というものが生まれるだろう。
テレビ
テレビの話に戻ると、テレビ画像の粗い粒子が「モザイク」で、それは「対象から距離をおく態度を許さない」かわりに、「存在全体の深層における参加と関与を要求する」ものであるということのようだ。19世紀に描かれたジョルジュ・レメンの上の絵というのは「非視覚的モザイク構造」ということになるのだろうか。ただし、現在の薄型テレビは、もはやブラウン管ではない。デジタルのクリアな画像は、人の顔の肌の感じとかがリアルに映りすぎていることなどもあって、かえって対象から距離を置いてしまうときがある。「改良されたテレビは、もはやテレビではない」とエッセイの中でマクルーハンはいっている。映画にしても、今はデジタル・エフェクトが使われているから、実写映像なのにCG(コンピュータ・グラフィックス)みたいな感覚が濃厚で、ヴァーチャルな感じが昔の映画とはまるで違う。画質というものが、一昔前とは質的に変わってしまったんじゃないかと感じることがある。
(了)
(2009年10月05日-13日)
[補記] 旧ホームページに載せていた文章です。古くなっている個所もあったので、本文を何カ所か訂正し、見出しを追加しました。例に出している街の写真は高校の頃にどこかのビルの屋上から撮ったもので、相当に古いもの。尻切れトンボで終わっていて、本当は、キュビズムから抽象絵画まで入れて続きを書くつもりだったんだけど、結局、書かずじまいだった。(2022年01月06日)